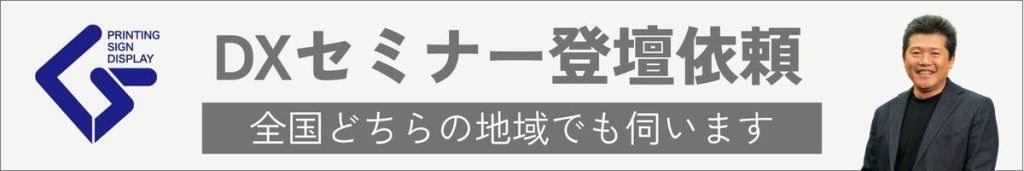ホームページは作った方が良い?
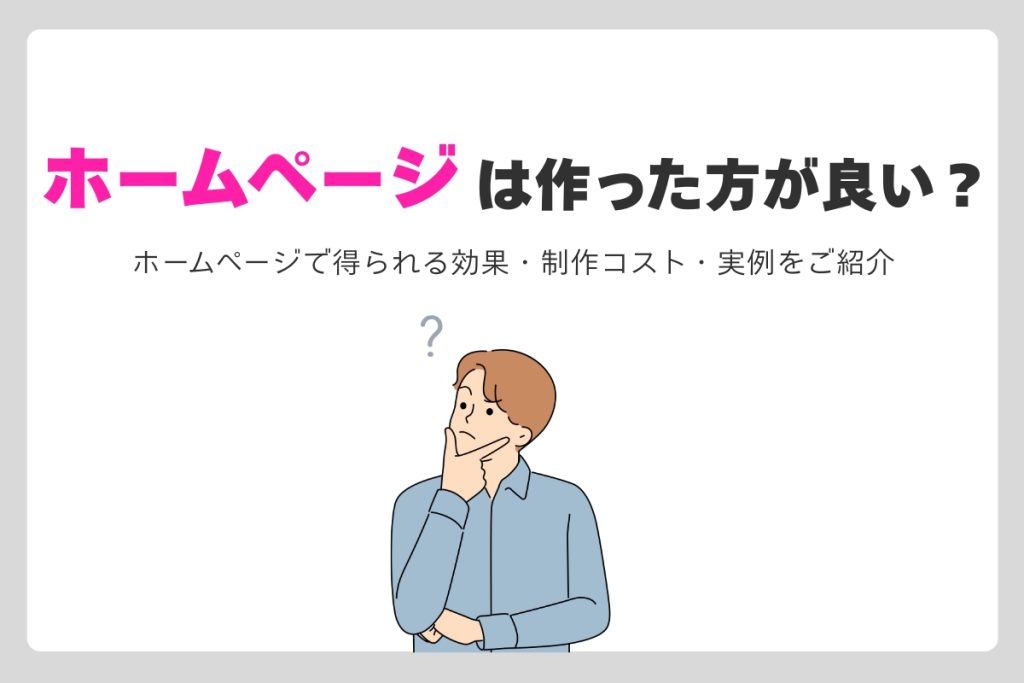
今や多くの人が、商品やサービスを探す際にまずインターネットで検索を行う時代です。ところが、まだ自社のホームページを持っていない企業も少なくありません。ホームページがなくても従来の人脈や紹介で取引が成り立つ場合もありますが、情報収集のスタート地点が変化した今、その状況は大きな機会損失につながりかねません。本記事では「ホームページは本当に作った方が良いのか?」という問いを出発点に、その必要性と活用方法について分かりやすく解説していきます。

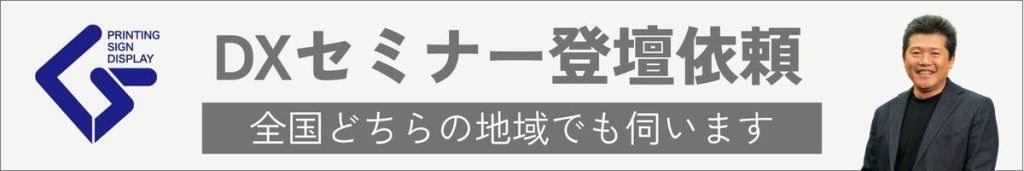
目次
ホームページは作った方が良い?
「ホームページは作った方が良い」と言われても、まだ持っていない企業は少なくありません。理由としては「紹介や口コミで仕事が成り立っている」「営業訪問で十分」「ネット販売はしていない」「コストがかかる」といった声がよく挙がります。確かに一昔前まではそれでも問題なく事業を運営できました。しかし現代では、顧客や取引先がまず最初に行う行動はインターネット検索です。情報が見つからなければ、検討のテーブルにすら乗らない可能性があります。
ホームページは単なる広告や飾りではなく、信頼性を担保し、会社の存在を正しく伝えるための入り口です。本記事では「なぜ今ホームページが必要なのか」「実際にどんな効果があるのか」を解説しながら、これからの時代における役割を整理していきます。
なぜ今、ホームページが必要なのか?
現代においてホームページが重要視される理由は、情報収集の手段が根本的に変化したからです。以前は紙のパンフレットや営業担当者の紹介、展示会での名刺交換が情報の入り口でした。しかし今は、誰もがスマートフォンやパソコンを使い、インターネットで比較検討を行うようになりました。BtoBであっても「気になる企業を検索して調べる」行動は当たり前になっており、特に若い購買担当者ほどその傾向が強いといわれています。
このような状況でホームページを持たないということは、存在していないのと同じリスクを背負うことになります。営業担当がどれだけ熱心にアプローチしても、相手が検索した際に情報がなければ「実態が分からない企業」と判断され、取引の候補から外されてしまうことも珍しくありません。
さらに信頼性の観点でも、ホームページは欠かせません。検索しても出てこない企業より、最新の情報が整理されたホームページを公開している企業の方が信頼されやすいのは当然です。つまり今の時代、ホームページは「信用の入り口」であり、顧客との接点を作る最初の手段なのです。
ホームページを持つと、どんな効果がある?
ホームページを持つことで得られる効果は大きく分けて3つあります。以下で詳しくご紹介します。
信頼感を与える
ビジネスにおいて第一印象は非常に重要です。ホームページがあるというだけで「しっかりと活動している会社」という印象を与えることができます。会社概要や沿革、代表挨拶が整っていれば、初めての取引で相手に安心感を持ってもらえます。逆に、ホームページが存在しない、あるいは何年も更新されていない場合、「事業を継続しているのか分からない」「古い体制のままではないか」と疑念を抱かれる可能性が高まります。
強みを正しく伝える
営業やパンフレットだけでは伝えきれない自社の強みも、ホームページなら写真や動画、導入事例を交えて分かりやすく発信できます。例えば製造業であれば工場設備や製造工程の紹介、印刷業であれば仕上がりのサンプルや納品事例を掲載することで、説得力を大きく高めることができます。強みを整理して公開する作業自体が社内の情報整理につながり、営業活動や採用説明にも役立ちます。
営業や採用を効率化する
ホームページは24時間365日稼働する「営業マン」であり「採用担当者」です。サービス紹介や注文の流れなどを掲載しておけば、同じ説明を繰り返す手間を削減できます。採用活動でも、仕事内容や職場の雰囲気を知ってもらうことで応募者とのミスマッチを防ぎ、効率的に人材を集められます。このように、ホームページは人材や時間の不足を補い、業務効率を改善する役割を果たします。
存在を知ってもらえるきっかけになる
ホームページは、まだ取引したことのない人に会社や店舗を知ってもらうきっかけにもなります。名刺や紹介だけでは届かない層に、検索を通じて見つけてもらえる可能性が広がります。特に地域名やサービス名と組み合わせた検索では、実際にニーズを持つ人に見つけてもらえる効果が期待できます。
マーケティングの幅が広がる
ホームページがあることで、WEB広告やSNSと組み合わせた本格的なマーケティング施策が可能になります。広告を出してもリンク先がなければ効果は限定的ですが、専用のページを用意すれば見込み顧客に必要な情報を的確に届けられます。アクセス解析を行うことで、どの情報が注目されているかを把握し、次の施策につなげることもできます。
ユーザーの疑問解消ツールとして機能する
ホームページは、ユーザーが抱える疑問や不安を解消するためのツールとしても効果的です。例えば「よくある質問」を設置すれば、問い合わせ前に解決できることが増え、顧客の安心感につながります。実店舗を持つ企業なら、アクセス方法や駐車場情報を掲載するだけで来店のハードルを下げられます。飲食店であればメニューを掲載することで来店意欲を高める効果があります。このように、ホームページは顧客の行動を後押しする大切な役割を果たすのです。
ホームページ制作に必要な経費とは?
「ホームページを作ろう」と決めたときに、まず気になるのは費用面です。ホームページ制作には初期費用とランニングコストの2種類がかかります。どのような規模のサイトを目指すか、外注するのか社内で作成するのかによって金額は大きく変わりますが、最低限押さえておきたい経費の目安は次の通りです。
初期費用
ホームページを立ち上げるために必要なのが初期費用です。ドメイン取得費用(年間1,000円前後〜)、サーバー契約費用(月額1,000円程度から)、そして制作費用が含まれます。制作を外注する場合は数十万円規模になることもありますが、CMS(WordPressなど)のテンプレートを使えば、比較的低コストでの構築も可能です。さらに必要に応じて写真撮影やライティング、デザインカスタマイズといった費用が加わることもあります。
ランニング費用
ホームページは作って終わりではなく、運営を続けるために維持費が発生します。主なものはドメイン更新料、サーバー利用料、そしてセキュリティのためのSSL証明書(無料のものもあります)です。小規模なサイトであれば、年間数千円〜数万円程度のランニングコストで十分に維持することが可能です。
オプション費用
SEO対策や広告運用、アクセス解析の導入など、より効果を高めたい場合には追加の費用が発生します。例えば専門業者にSEO改善を依頼すれば月額費用が必要になりますし、WEB広告を運用する場合には広告費用に加えて運用代行費用がかかる場合もあります。目的に合わせて「どこまで投資するか」を検討することが大切です。
運営を続けるために必要な取り組み
ホームページは公開したら終わりではありません。むしろ運営を続けて初めて価値が出てくるものです。そのために必要な取り組みを整理してみましょう。
定期的な更新
ニュースや事例紹介、製品情報の追加など、定期的に更新することで「今も動いている会社」であることを伝えられます。更新が何年も止まっていると、信頼感を損なうリスクがあります。月に1回程度でも新しい情報を加えるだけで効果は大きく変わります。
問い合わせ対応
問い合わせフォームを設置したら、それに応じる体制も整えておく必要があります。フォームからの問い合わせは、電話よりも気軽に送られるケースが多いため、迅速に対応できる体制を用意することで信頼度が高まります。問い合わせが来てからのスピードが、契約の成否を分けることもあります。
特に、ユーザーは複数の企業を比較検討しているケースが多いため、返信が遅いとその間に他社へ依頼が決まってしまう可能性があります。早い段階で誠実に対応することが、信頼を獲得し選ばれるための大きなポイントになります。
アクセス解析
Google Analyticsなど無料の解析ツールを利用すれば、ホームページにどれだけの人が訪れ、どのページがよく読まれているかを把握できます。アクセス状況を分析することで、どんな情報が求められているのかを理解し、改善につなげることができます。
ただし、Google Analyticsは専門用語や設定が多く、初めて扱う人にはやや難しいと感じられるかもしれません。その場合は、サーバー会社が提供しているアクセスレポートや、WordPressのプラグインで表示できる簡易解析機能を活用するのも一つの方法です。まずは「アクセス数」「人気のあるページ」といった基本情報だけを確認するだけでも十分効果があります。段階的に慣れていくことで、より高度な分析にも取り組みやすくなります。
セキュリティ管理
ホームページを安心して利用してもらうためにはセキュリティ対策も欠かせません。パスワード管理やシステム更新を怠ると、改ざんや不正アクセスのリスクが高まります。定期的なバックアップを取ることも重要です。
【実例】当社のホームページリニューアルで感じたメリット
当社のホームページは当初、代表の小泊と他スタッフ1名にて自作したものでした。2名ともそれまでホームページ制作をしたことがなかったため、最低限の要素があるシンプルなホームページを運営していました。しかし数年かけて段階的にリニューアルを行い、製作事例紹介などを通じて随時情報を発信するようにしたことで、大きな変化がありました。
まず、過去の事例を見たお客様からの問い合わせが増えました。「似たような看板の製作をお願いしたい」「この事例と同じ仕様で製作した場合の見積が欲しい」といった声をいただくようになり、ホームページが新しい案件を生み出す大きなきっかけになっています。
また、DXに関する取り組みや情報を発信することで、「本格的にDXを推進している会社」という認知が広がりました。実際にセミナーなどに参加された方から「ホームページを見て御社の姿勢がよく分かった」と声をかけていただくことも増え、信用やブランディングにもつながっています。
このように、自社のホームページを見直して情報発信を始めたことで「問い合わせの増加」と「認知度の向上」という2つの成果を実感しています。最初はシンプルなホームページからでも、改善を重ねることで確かな効果を得られるということを実体験としてお伝えいたします。
まとめ
ホームページを持つことは、今や企業にとって「あると便利」ではなく「なくてはならない存在」になっています。確かに制作には初期費用やランニングコストがかかりますし、公開後も更新や問い合わせ対応など手間がかかります。しかし、それらは決して過大な負担ではありません。小規模であれば年間数千円から維持でき、工夫次第でコストを抑えながら運営していくことが可能です。
重要なのは「作って終わり」ではなく、そこから少しずつ改善を積み重ねていくことです。まずは会社の基本情報やサービス内容を掲載するだけでも、取引先や顧客にとって安心感を与えられます。その後、事例紹介やニュースを発信していけば、営業や採用の効率化、そして新規案件の獲得へとつながっていきます。
実際に当社でも、シンプルなホームページから始めてリニューアルと情報発信を重ねたことで、問い合わせが増え、信用や認知度の向上につながりました。「費用や手間をかけるだけの価値がある」と自信を持って言えます。
「ホームページは作った方が良いのか?」という問いへの答えは間違いなく「はい」です。まだ持っていない方も、この機会にぜひ検討してみてください。少しの投資と取り組みが、将来の大きな成果や信頼につながっていきます。