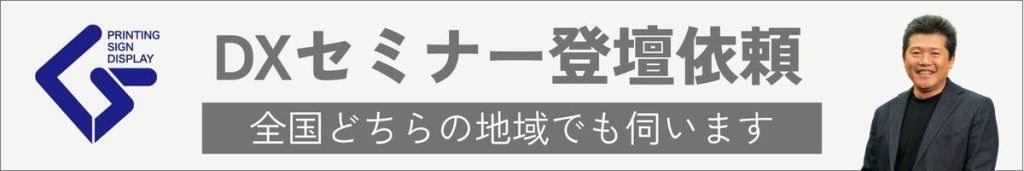【ホームページのアクセス解析】最初の一歩

前回のコラムでは、「ホームページを集客に活かすためには、まず“アクセス数を知ること”が大切」というお話をしました。アクセス数を知ることは、ホームページを改善していくための第一歩。しかし、実際に数字を見られるようになっても「次に何をすればいいのか」で悩む方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、アクセス解析の“最初の一歩”として、数字をどう読み取り、どんなヒントを得られるのかを解説します。前回が「アクセスを“知る”」だったとすれば、今回は「数字を“使いこなす”」第一歩です。

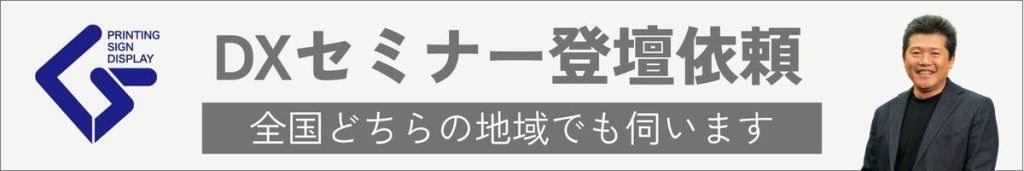
目次
アクセス数を見ても「多い・少ない」は判断が難しい
アクセス解析で数字が見られるようになると、つい「アクセスが多い=良い」「少ない=悪い」と考えがちです。ですが、実際にはその判断はとても難しく、会社の業種・目的・方針によって“良し悪しの基準”が変わります。
例えば、BtoCの通販サイトなら「アクセス数が多いほど販売機会が増える」と考えられますが、BtoB企業のサイトでは「アクセス数よりも、見に来た人の質(問い合わせや購入、採用につながったか)」が重要になることもあります。
つまり、数字だけを見ても“良いか悪いか”は一概に判断できません。そのため、まずは数字を評価するのではなく、他社と比べて今の自社の立ち位置を知ることから始めましょう。 次の章では、その比較が簡単にできるツール「シミラーウェブ」をご紹介します。

まずは「競合と比べてみる」ことから始めましょう
アクセス数を確認できるようになっても、「この数字は多いのか、少ないのか?」という判断は、最初はとても難しいものです。社内に分析に詳しい人がいない場合は、なおさらです。
そこで役立つのが、Similarweb(シミラーウェブ)というツールです。
シミラーウェブとは?
シミラーウェブは、ウェブサイトやアプリのアクセス状況、市場動向、競合他社のデジタル戦略などを分析できる「アクセス解析・競合分析ツール」です。URLを入力するだけで、
- アクセス数の推移
- どこから流入しているか(検索 / SNS / 他サイト / 広告など)
- 訪問ユーザーの属性(地域 など)
といった情報を、推計値として把握できます。無料版と有料版がありますが、無料版でも多くの情報が得られます。 また、自社の情報を得られるだけでなく競合他社サイトのURLを入力すれば、自社と他社を比較することもできます。
これらは、市場での自社の立ち位置を客観的に見る手がかりになります。
▼シミラーウェブのTOP画面(無料登録している場合)
 赤枠で囲っている箇所にサイトURLを入力すると、そのサイトのアクセス状況が確認できます。自社サイトに加えて競合他社サイトのURLを追加入力すると、比較ができます。
赤枠で囲っている箇所にサイトURLを入力すると、そのサイトのアクセス状況が確認できます。自社サイトに加えて競合他社サイトのURLを追加入力すると、比較ができます。
「比較」だけでなく、“今の立ち位置”を知ることが目的
最初の段階では、深い分析はまだ必要ありません。まずは次のような視点が持てればOKです。
- 競合よりアクセスが多い → 認知はある程度できている可能性
- 競合よりアクセスが少ない → まずは知ってもらうための取り組みが必要
この「大まかな立ち位置」を知ることで、次に取るべき方向性が見えやすくなります。
▼シミラーウェブで4サイト比較時の一例

様々な指標が表示されるので最初は混乱してしまうかもしれませんが、まずは一番上の「月間セッション数」に注目してみましょう。自社サイトが他社サイトよりアクセスが多いのか、少ないのかが数字で確認できます。
比較したサイトの中で一番「月間セッション数」が多ければ、”一歩リード”と捉えて良いでしょう。逆に比較したサイトの中で自社サイトの「月間セッション数」が少ない場合は、”改善の必要がある”と考えましょう。


当社マーケティング部スタッフ コメント
シミラーウェブは無料版でも「アクセスの規模感をつかむ」には十分活用できます。有料版にすると見られる情報は増えますが、なぜ有料化する必要があるのかという、有料化の価値を社内に説明するのは最初の段階では難しいことが多いです。情報が増えても、それを活かすための知識や判断軸が追いつかないケースもあるため、まずは「無料版」で競合と比べた時の“現在地”を感じ取るだけで十分です。
それだけでも、「もっと認知を広げないといけない」「集客の入口となるページを増やそう」など、次につながる気づきが生まれます。
ちなみに当社では、無料版を使用しており、無料版で十分だと考えています。また、シミラーウェブを使用する頻度は2.3カ月に1回程度です。
次のステップ:GA4で「どこから来ているのか」を見てみましょう
シミラーウェブで「自社がいまどの位置にいるのか」をつかんだら、次は「ホームページに来た人がどこから来ているのか」を見てみましょう。 ここで使うのが、Google の無料ツール 「GA4(Google Analytics 4)」 です。
前回のコラムでは、まず押さえるべき基本指標として以下の4つをご紹介しました。
- アクセス数(PV数): ページが合計で何回見られたか。お店で言えば「のれんをくぐって店内を見て回った回数」です。
- 訪問者数(UU数): 何人の人が訪問しているか。同じ人が何度見ても「1人」として数えられます。新しいお客さんの数を知るための指標です。
- 人気ページ: どのページがよく読まれているか。お客様が本当に求めている情報が見えてきます。
- 流入経路(チャネル): 訪問者がどこから来たのか。検索なのか、SNSからなのか、広告からなのか。
今回はこの中から特に重要な 「流入経路(チャネル)」 に注目してみましょう。チャネルを確認することで、SNS・広告・ブログなど自社の取り組みと結果を照らし合わせ、「どこに力を入れるべきか」が見えてきます。
GA4でチャネルを確認する手順
GA4にログインしたら、左側メニューから 「レポート」 → 「集客」 → 「トラフィック獲得」 をクリックします。


この画面で「セッションのデフォルトチャネルグループ」という項目を確認すると、どの経路からアクセスが来ているのかが一覧で表示されます。英語で表記されている各指標については後述します。
GA4の主なチャネル分類
GA4では、アクセスの流入元をいくつかのグループに自動分類しています。「セッションのデフォルトチャネルグループ」で表示される主な指標の種類は以下の通りです。
| チャネル名 | 意味・主な流入元 |
| Organic Search | GoogleやYahoo!などの検索エンジンからの自然検索からの訪問 |
| Direct | URLを直接入力、またはブックマークからの訪問 |
| Referral | 他のサイトにあるリンクを経由しての訪問 |
| Paid Search | Google広告などの検索連動型広告からの訪問 |
| Display | バナー広告やディスプレイ広告経由の訪問 |
| Organic Social | Instagram、X(旧Twitter)、Facebookなどの有料広告ではないSNSからの訪問 |
| メルマガやメール内のリンクからの訪問 |
この分類を見れば、「どの経路が強いのか」「どの取り組みが結果につながっているのか」 が一目で分かります。
当社マーケティング部スタッフ コメント
初めてGA4を使うときは「画面が難しそう…」と感じる方も多いですが、
実際にはこの「トラフィック獲得」だけでも十分に活用できます。
どのチャネルからアクセスが多いかを見るだけで、
SNS・広告・ブログといった社内の取り組みのどこが成果につながっているかが見えてきます。
まずは毎月1回チェックして、「数字の変化」に気づくことから始めてみましょう。
チャネル分析を活かして、自社の取り組みを振り返ってみよう
GA4で「どこからアクセスが来ているのか」が分かるようになると、次にやるべきは数字と日々の取り組みを結びつけて考えることです。どんな経路が成果につながっていて、どんな部分が思うように結果が出ていないのかを見ていくことで、改善の方向性が見えてきます。
例えば、SNS更新・WEB広告・ブログ投稿など「頑張っているのに成果が見えにくい」と感じている活動も、GA4のチャネルデータと照らし合わせることで、課題が具体的に見えてくることがあります。
次に、よくある3つのケースを例に、どんな「ズレ」や「気づき」が生まれやすいのかを見ていきましょう。
Instagram を毎日更新しているのに、サイトに人が来ていない場合(チャネル:Organic Social)
GA4上では、有料プロモーションを除くInstagramやX(旧Twitter)などSNSからのアクセスは「Organic Social(ソーシャル)」というチャネルに分類されます。つまり、この数値が少ない場合は、SNS経由でホームページに来ている人が少ないことを意味します。
実はこのケース、とても多いです。原因はいくつか考えられます。
- フォロワーが少なく、投稿がそもそも見られていない
- 投稿文やハッシュタグに「検索されやすい言葉」が入っていない
- プロフィールや投稿にサイトへのリンク導線がない(=Instagram内で完結してしまう)
Instagramの投稿は、画像作成・文章作成・撮影など、時間も手間もかかります。 しかし、もし「サイトに来てもらうこと」が目的なのであれば、投稿数が増えても成果にはつながらないことがあります。
逆に目的が「Instagram内でのファン作り」なら、それはそれで正しい取り組みです。 大切なのは、“何を目的に投稿しているのか” を会社として共通認識を持つことです。
もしサイト流入がほとんどないのに「毎日投稿が必須」になっている場合は、 GA4の「Social」の数値を上司に見せることで、投稿体制を見直すきっかけを作ることもできます。

WEB広告費をかけているのに、広告からのアクセスが少ない場合(チャネル:Paid Search)
Google広告やYahoo!広告など、費用をかけて掲載する広告からのアクセスはGA4上では「Paid Search(ペイドサーチ)」に分類されます。 この数値が低い場合は、広告が表示されていない・クリックされていないなど、何らかの問題が起きている可能性があります。
特に「広告代理店に運用を任せている場合」は注意が必要です。 例えば、月に30万円の広告費をかけているのに、広告からのアクセスが月100件以下だったとしたら、どうしてそうなっているのか疑問を持つことが大切です。(クリック単価にもよります)
また、アクセスは多いのにお問い合わせや注文が極端に少ない場合は、次のような要因が考えられます。
- 広告のターゲット設定が合っていない
- 広告の掲載場所(媒体)が適切ではない
- 広告の効果測定がきちんと設定できていない
- そもそもその業種は広告で集客しにくい
このとき大切なのは、「広告費を使って成果が出ているのか?」を数字で確認する習慣を作ることです。 改善の話ができない状態は、とても危険です。 WEB広告は専門用語が多く、とっつきにくい印象がありますが、わからないことを放置すると「何に投資しているのか」さえ分からなくなってしまいます。
不明点は小さなことでも代理店に質問して、自社の大切な予算を有効に使えるようにしましょう。

ブログを書いているのに、検索から来る人が増えていない場合(チャネル:Organic Search)
Googleなどの検索エンジン経由でのアクセスは、GA4上では「Organic Search(オーガニックサーチ)」に分類されます。 ブログ記事からの流入が少ない場合は、このチャネルの数値を確認してみましょう。
ブログは、上手に活用できれば検索からの流入を増やせる強力な手段です。 しかし、次のような状態だと成果につながりにくいことがあります。
- 誰に向けて書いているかが曖昧
- 伝えたいことだけを書いてしまっている
- 検索される言葉(キーワード)の視点が入っていない
ブログは「書くこと」自体が目的になってしまうと効果が薄くなりやすいです。 企業としてブログを書くのであれば、「書くこと」ではなく「読まれること」を目的にしましょう。
また、検索からの流入を増やすには、“ユーザーが実際に検索する言葉”に合わせて内容を作る必要があります。 ただし、これはある程度の経験や知識が必要なため、最初のうちは成果がすぐに出なくても落ち込む必要はありません。
「検索されやすい言葉を知る」ことについては、次回以降のコラムで詳しく紹介します。

まとめ
アクセス解析は「結果を評価するためのツール」ではなく、“気づき”を積み重ねていくためのツールです。数字を見ること自体が目的ではなく、数字から「なぜそうなっているのか」を考えることで、次のアクションが見えてきます。
今回のように、まずは「自社の立ち位置」や「どこからアクセスが来ているのか」を知ることは、最初の大切なステップです。そこから少しずつ、どんなページがよく見られているのか、どんな人が訪れているのか、どんな行動をしているのか――と理解を深めていくことで、ホームページ改善の精度は確実に高まっていきます。
今後もこのコラムでは、アクセス解析を活用してホームページをより良くしていくための視点や考え方を、段階的に紹介していく予定です。数字に苦手意識を持たず、“数字の裏にある意味を読み取る”姿勢で、ぜひ一歩ずつ進めていきましょう。